「支店長になれば、もう安心だと思っていた」
そう語ってくれたのは、かつて誰もが一目置いた元先輩。
今では関連会社に出向し、“アドバイザー”という肩書を名乗っているものの、実質的な仕事は「何もアドバイスを求められていない」と言います。
銀行の世界では、支店長はゴールではなく、通過点。
それどころか、「あのとき支店長になったのがピークだった」と振り返る人も少なくありません。
本記事では、銀行員の一生に潜む“出世レース”と“その後のリアル”を、昇格の裏にある情報戦や社内政治、そして“出向”という現実まで含めて赤裸々に描きます。
定年まで銀行員として生き残れるのは何人なのでしょうか?
第1章|同期で一番最初に支店長になる人の特徴とは?
「聞いた? ○○が支店長になったらしいぞ」
銀行内でこの話題が出たとき、あなたはどんな気持ちになるだろうか。
嬉しい? 焦る? それとも、悔しい?
銀行員にとって、“同期の中で最初に支店長になる”というのは、単なるポジションの話ではなく、「出世コースに乗った」ことの象徴だ。
■ 出世競争の第一関門、それが“支店長”
銀行によって細かな違いはあるが、支店長昇格のタイミングは概ね以下の通り:
- 🕰 40代前半〜中盤で郊外の支店長に就任できれば順調
- 🕰 それ以降にズレこむと「次の昇格の波」が難しくなる
- 🕰 50歳を過ぎても未経験なら「出世競争からは外れた」と見なされる
つまり、支店長になるのが“早いか、遅いか”は、その後のキャリアにとって致命的な分かれ道になるのだ。

■ 「実力だけじゃない」──なぜ“あの人”が先に支店長?
読者のあなたも、こんなことを思ったことがあるかもしれない。
「同期のAは、正直そこまで営業成績よくなかったのに」
「むしろBの方が実力あると思ってた」
あんなに優秀だったBさんが支店長になれず、関連会社に出向したと聞いたとき、胸がざわついた──。あれは、他人事じゃない。
だが、銀行の出世競争は実力主義だけではない。
むしろ、“支店長になれるかどうか”には次のような要素が強く絡んでくる。
🔍「同期最速の支店長」になる人の共通点とは?
| 要素 | 解説 |
|---|---|
| ✅ タイミング | ポストが空いていたかどうか |
| ✅ 社内政治力 | 上司・人事部・役員への見え方 |
| ✅ 評価の安定感 | 異動先でも大きく外さない安心感 |
| ✅ 過去の異動歴 | 「昇格ルート」とされる部署を経てきたか |
銀行の人事は“パズル”。
実績の良し悪しだけでなく、「今、動かして問題がない人かどうか」が昇格判断に大きく影響する。
■ 早く支店長になれば“安泰”か?
答えは、NOだ。
たとえ支店長になっても、その先の未来には、
- 不祥事のリスク
- 支店の格による評価差
- ポストの競合者
が立ちはだかる。
そもそも出る杭は打たれる文化。
出過ぎると、残るところが面白い。
だからこそ、最初の支店長昇格はスタートラインでしかない。
✍️ 銀キャリ的ひと言
銀行の昇格は「努力×実績×戦略×運」。
どれか一つ欠けても、次のステージに行けない。
早く支店長になることは“幸運”ではなく、“戦略的な成果”でもあるのだ。
第2章|昇格人事は“ドミノ倒し”で決まる
銀行の昇格人事は、よく「ドミノ倒し」に例えられます。
きっかけは、年に一度の役員人事。
ここで1つピースが動くと、その下の管理職たちも連鎖的にポストを移動させられます。
■ 昇格ドミノの基本構造
- 役員の退任・交代が決定(株主総会・取締役会)
- → 部長クラスが役員へ昇格
- → 大型店舗の支店長が部長ポストへ異動
- → 副支店長が支店長へ昇格
このように、ひとつの動きが連鎖し、最終的に現場の支店長ポストが空くのです。
「今、どこかの役員が動く」=「どこかの副支店長が支店長になるチャンスが巡ってくる」
■ タイミングを逃すと“波”に乗れない
このドミノ式人事で重要なのは、タイミングと自分のポジション。
つまり、
- 昇格の“波”が来たとき、
- 自分がその波に乗れる位置にいるか
それがすべてです。
たとえば、評価は高くても――
- 支店の成績が振るわない
- 異動直後で「まだ早い」と見なされる
- 上司がプッシュしてくれない
こんな状況にいれば、ドミノの波はスルーしていきます。
■ 「昇格できる人」と「波を逃す人」の分かれ道
| 昇格できる人 | 波を逃す人 |
|---|---|
| ◎ 昇格ポストが空いた直後に適任者として配置されている | × 波が来たときに異動直後 or 低評価ポジション |
| ◎ 人事部・役員との関係も安定 | × 推薦者がいない or 強く推されない |
| ◎ 昇格候補リストの上位に入っている | × 評価は高くても「旬を過ぎた」と思われている |
本部マネージャーから支店長に昇格目前だった先輩が、異動のタイミングを一つ外しただけで関連会社に出向となった。
人事とは、残酷なほど“位置とタイミング”で決まるゲームだ。
✍️ 銀キャリ的ひと言
銀行の昇格は、「評価される」ことと「タイミングをつかむ」ことの両立が必要。
どんなに優秀でも、波が来たときに“その場所にいない”と、出世レースはそこで終わる。
第3章|支店長候補たちの“情報戦”と“読み合い”
支店長への昇格は、単なる実力や成績だけでは勝ち取れません。
本部マネージャーや副支店長クラスの人材たちは、「次にどこのポストが空くのか?」を常に気にしています。
「あの支店の支店長は3年目。そろそろ動く頃だな…」
「副支店長のまま5年って、あの人そろそろ昇格するんじゃ?」
そんな会話が、昼休みや喫煙所で自然に飛び交う──。
昇格の鍵は、“誰よりも早く空くポストを察知する力”も必要。
■ 支店長ポストの“任期パターン”
支店長の任期には、銀行ごとの“なんとなくのルール”があります。
- 都市部の支店:おおよそ2〜3年で異動
- 地方の中規模支店:3〜4年で異動
- 海外や本部経由の戻り先支店:半年〜1年のケースも
支店長候補たちは、このパターンを踏まえて「どの支店がいつ空くか」を独自に予測しています。
■ 情報収集と“人事レーダー”の精度が勝敗を分ける?
支店長候補たちは、社内に「情報網」を持っていることが多いです。
- 仲の良い同期・後輩・先輩から支店の様子をヒアリング
- 人事部にさりげなく“自分の動向”を印象づける
- 過去の異動傾向から、誰がどのポストを狙っているかを分析
しかし──
いくら情報を集めても、最終的に決めるのは“人事部”。
いろいろ言いますが、競馬の予想屋さんだらけ。
どれだけ先を読んでいても、昇格の波が来た瞬間に“準備万端の状態”でなければ意味がありません。
■ 昇格は「2年目以降」が勝負
支店長候補にとって、着任から2年を経過したあたりからが勝負所。
特にコンプライアンス違反は致命的。
本人の不注意だけでなく、部下のトラブルも含めて「昇格延期」「待機リストから除外」というケースは珍しくありません。
■ 支店長待ちリストは“生きている”
銀行の人事部には、実質的な「昇格予備軍リスト」が存在しています。
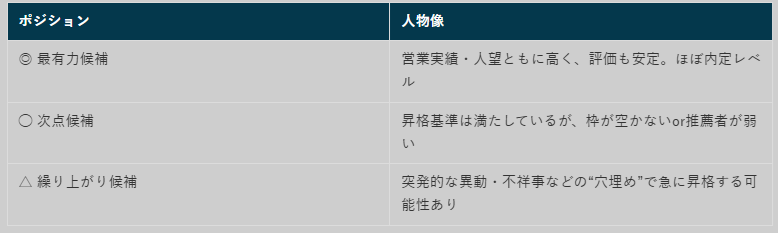
このリストは固定ではなく、日々変動しています。
第4章|支店長でも神頼み|部長・役員昇格の不確実性
「支店長になればもう安泰」──そんな時代は終わりました。
支店長になったとしても、その先の部長・役員昇格は、実力だけではどうにもならない“運と不可抗力の世界”。
「成績は優秀。評価も高い。次は自分の番だと思っていた──」
そんな支店長が、ある日突然、出向を告げられる。
■ 昇格が吹き飛ぶ“3つの外的要因”
部長・役員昇格の判断には、本人の努力以外にも様々な要因が影響します。
- ① 部下の不祥事
本人に非がなくても、店舗でトラブルが起きれば「管理不足」として昇格が延期される。 - ② 支店でのコンプライアンス違反
小さなチェック漏れも「支店長の責任」。マイナス評価となり波に乗れない。 - ③ 推薦が割れたとき
部長昇格候補が複数いた場合、「誰を上げるか」は役員同士の調整で決まる。推薦力の差で落選も。
■ 部長になるには“順番”がすべて
部長ポストは非常に限られており、役員の退任とリンクした少数のイスしか存在しません。
そのため、
- 上位の誰かが辞めるか異動しない限り、空きが出ない
- 別の支店長が強く推薦されていれば、その人が優先される
- タイミングを逃すと、もう“チャンスがない”年齢に突入する
まさに“神頼み”。ここで昇格できるかどうかは、本人の実力を超えた運の領域に入ってきます。
■ 役員昇格は“公開されないレース”
さらにその先の役員昇格は、もはや“誰と戦っているのか分からないレース”。
候補者同士が表には出ない中で、
- 社長・副社長からの引きがあるか
- 過去の実績・出身部署・経歴がどう評価されるか
- 会社の方針(若返り・多様化・改革派登用など)
といった要素で、突然指名されるか、静かに外されるかが決まります。
支店長までは「見える昇格」。
部長から先は「見えない選抜」──。
「あれ?あの人がコンプラ部長?」と思わず心の中でつぶやいた──
そんな不可解な人事すら、銀行では珍しくない。
第5章(最終章)|出向・役職定年|キャリアの着地と“次の選択”へ
銀行員としてのキャリア──
その“ゴール”が、必ずしも晴れやかなものとは限りません。
順調に支店長へ昇格し、評価も高く、社内での存在感も十分。
それでも、多くの銀行員がたどり着くのは「出向」、そして「役職定年」という現実です。
■ 出向という“静かな幕引き”
55歳を前に、「次は関連会社へ」と静かに告げられる──。
その瞬間から、銀行本体のキャリアは“終了”となります。
- ⚠️ 担当はあるが裁量はない
- ⚠️ 組織の外で“銀行の人”として働く違和感
- ⚠️ 給与は20〜40%減も珍しくない
執行役員にまでなっても、これは避けられないのかもしれません。
「支店長だった自分が、また営業マンに?」
そんな声が、出向先では日常的に聞こえてきます。
■ 役職定年という“立場の消失”
さらに60歳を前に、役職は外れ「シニアアドバイザー」「専任職」などの肩書きに変わります。
業務量は軽くなる一方で、影響力・収入・部下の有無すべてが縮小。
- 周囲の視線:「昔はすごかった人」扱い
- 自己認識:「もう“居場所”がない」感覚
- 次の人生:「今さら転職?起業?」という不安
これは、誰にでも訪れうる未来です。
■ 「どう終えるか」は「どう生きるか」
銀行員としての人生をどう締めくくるのか──
その答えは、支店長になった時点で考えておくべきです。
- ◎ いつか来る出向を前向きに受け入れる準備
- ◎ 本部や現場で“今いる場所”をどう使い切るか
- ◎ 銀行の外でも通用するスキル・人間関係を意識する
“出世”がすべてではない。
でも、“どう終えるか”は、その人がどう生きてきたかを映す鏡でもあります。
✍️ 銀キャリ的ひと言
「支店長になって終わり」ではなく、“その先”をどう選ぶかが、キャリアの本質。
次の記事では、支店長経験者が出向先で直面するリアルを紹介します。

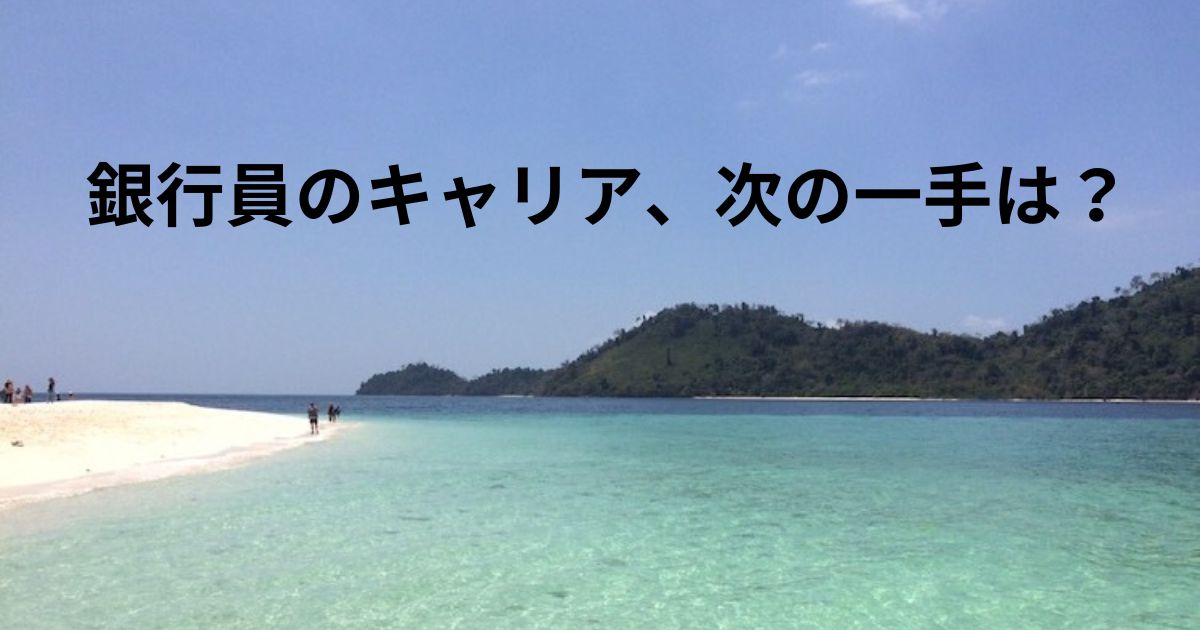
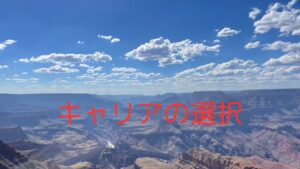
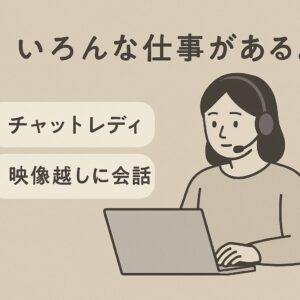
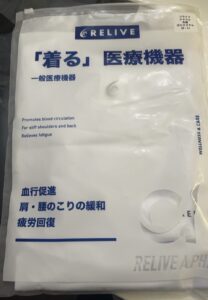
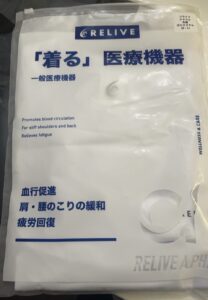
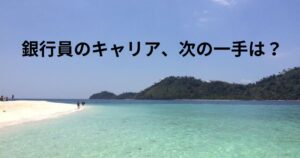
コメント